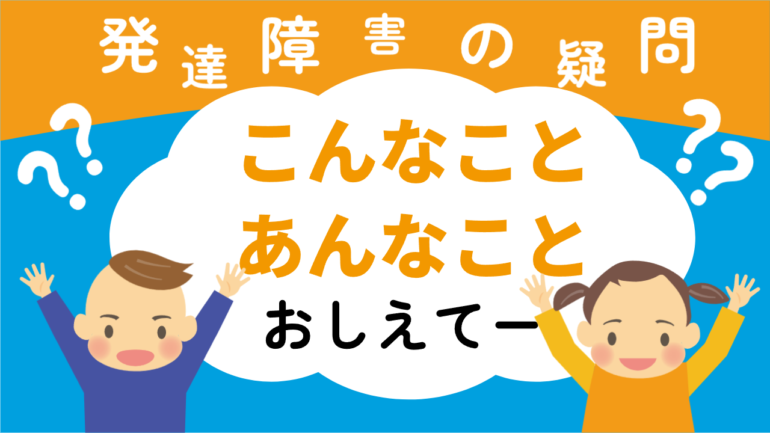こんにちは ゆる楽メンタルカウンセラーのへらいえつこです。
新年度、子どもが新しい先生・新しい環境に慣れるのと同じように、親の方も学校側に何をどう伝えていけばいいのか迷うことがあると思います。
特に発達障害のある子どもの場合、「どんなサポートが必要か」「どんな配慮があれば過ごしやすいか」を学校側に伝えることは、とても大切です。
でも、合理的配慮の伝え方に正解があるわけではありません。
伝えようとするあまり、かえって緊張してしまったり、「迷惑がられないだろうか」と心配になったりすることもあるかもしれません。

今回は、合理的配慮を伝えるときに意識しておきたいポイントと、心の持ち方についてお話します。
「正しく伝える」より、「伝わる形で伝える」
合理的配慮というと、「診断名を添えて、専門的に説明しなければ」と思うかもしれません。
でも、先生方が必要としているのは、専門的な説明よりも“具体的に何に困るのか”“どうすれば落ち着いて過ごせるのか”という情報です。

たとえば:
- 「聴覚過敏があります」よりも「チャイムや放送の音が苦手で、耳をふさぐことがあります」
- 「衝動性が強いです」よりも「列に並ぶときに待ちきれず、前に出てしまうことがあります」
こうした“日常の具体的な場面”に落とし込んだ伝え方のほうが、相手にもイメージが伝わりやすくなります。
その子の力を発揮しやすい環境を一緒に考える
合理的配慮をお願いすることに、どこか申し訳なさを感じてしまう方もいます。
ですが、配慮とは“特別扱い”ではありません。その子が持っている力を、無理なく発揮できるようにするための工夫です。
学校側に伝えるときも、「~してほしいです」と一方的に要望するのではなく、
「この子が安心して授業に集中できるように、こういった形を試せるかもしれません」など、“一緒に考える”スタンスを意識してみましょう。
そのほうが、先生にとってもプレッシャーが少なく、受け入れやすいものになります。
一度ですべてを伝えようとしなくていい
伝えたいことがたくさんあると、「最初に全部言わなきゃ」と思いがちです。
けれど、学校側も年度始めは多忙で、先生も新しい情報を一度に受けとるのが難しい場合もあります。
焦らず、まずは「伝える態度を示す」ことを大切にしてください。
そして、「困ったことがあれば、いつでも協力します」と一言添えておくと、今後のやり取りがしやすくなります。

“少しずつ伝えていく”“対話を続けていく”ことが、最終的には子どもにとっての安心につながっていきます。
親が自分を責めすぎないことも、子どもの支えになる
配慮をお願いしたのにうまく伝わらなかった、対応してもらえなかった…
そんなとき、「自分の伝え方が悪かったのかも」と自分を責めたり、「全然話を聞いてくれない」と学校に怒りを感じることがあるかもしれません。
けれど、支援や理解には“時間がかかること”もあるという前提を、どうか忘れないでください。
学校も先生も、すべてをすぐに理解できるわけではありません。
それでも、親があきらめずに「わが子にとって必要な支援」を伝え続けることは、必ず意味があります。
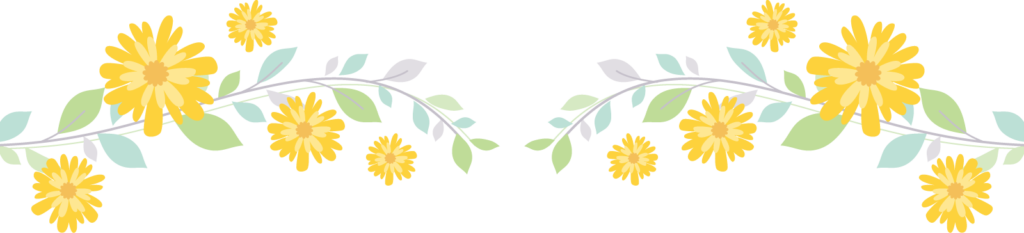
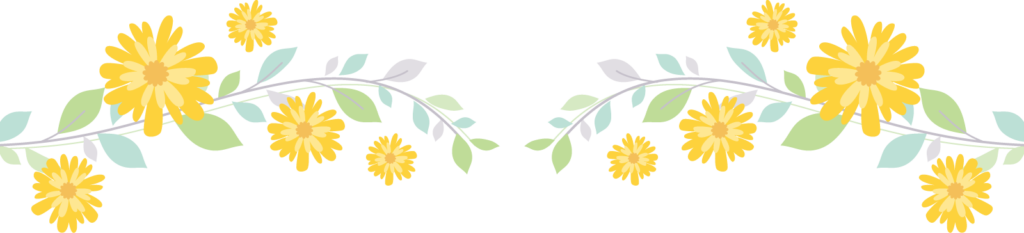
子どものためにと頑張っているうちに、自分の心が疲れてしまうこともあります。
もし今、「自分の気持ちがわからなくなっている」「もっと落ち着いて対応したい」と感じているなら、お試しカウンセリングでいまの思いを話してみませんか?
自分の軸を整える時間は、きっと子どもの安心にもつながります。
大人も子どももすべての人が自分を好きと思え、笑顔で子育てができるよう応援しています。
<この記事も読んでみて>